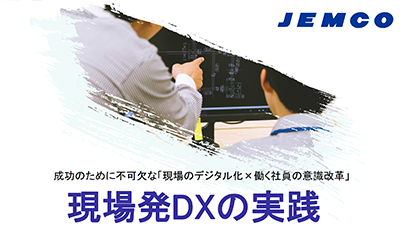生産の基本論~ものづくりの達人になるためにおさえるべきツボ~【第43回 数量の視覚化】
文責:ジェムコ日本経営 コンサルタント 原 正俊
皆さんは、「IE」という言葉をご存じでしょうか?IEは、Industrial Engineering の略称で「生産工学」などと呼ばれ、「生産性向上」と「原価低減」を行うものです。ジェムコでは、「IE」の考え方に関する情報をコラムでお届けしております。
43回目の今回は、「数量の視覚化」についてです。
「在庫の視覚化」と「数量の視覚化」
以前に容器の話をしましたが、容器で数量が分かるようにするということは一種の「在庫の視覚化」です。数量を数えなくても見て数が分かるようにするというのが「数量の視覚化」です。
「数量の視覚化」のための方法
設備の脇などで数量を数えるという作業を見かけることがよくあります。この数量を数えるという行為は付加価値を生み出しませんから、できるだけ無くさなくてはなりません。
計数装置(カウンター)のようなものを設備に取り付けて、自動的に数量をカウントして一定量だけ容器に払い出すことができれば一番簡単です。ただしこれはお金がかかります。
また、重量で測るということも考えられます。1個1個の重量が一定でばらつきがなければ、総重量から個数を割り出すことができます。あまり小さいモノや軽いモノには誤差が生じる危険性があるので不向きですが、この方式を採用している企業も結構あります。
アナログ的な視覚化
あとは、アナログ的な視覚化です。10個入りのトレーがすべて埋まっていれば10個です。トレーの数だけ数えればいいわけです。仕掛品が並ぶところに10個単位で区切りを入れることで、数えなくても見て数量がわかります。数量を計るのではなくて、置いたり並ぶことで数量が自動的にわかるような仕掛けをつくるのです。
部品や材料の倉庫でこのような「見て分かる方法」を採用しているところはたくさんあります。これは発注点管理にも活用できます。発注すべき数量までストックが減ると、何らかの発注を促すシグナルが現れます。そうすることで数えなくても見てわかるようになります。
数量が狂う可能性を改善することも大切
数量のチェックをしなくてはならないのは、数量が狂う危険性があるからです。根本的にその部分を改善することで、危険性を減らすことも必要です。そうすれば数える必要もなくなるのですから。