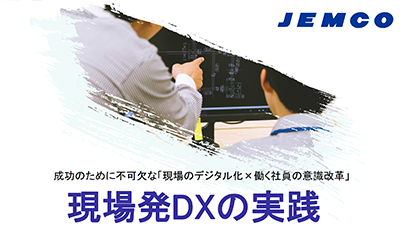生産の基本論~ものづくりの達人になるためにおさえるべきツボ~【第51回 検査のポイント①】
文責:ジェムコ日本経営 コンサルタント 原 正俊
皆さんは、「IE」という言葉をご存じでしょうか?IEは、Industrial Engineering の略称で「生産工学」などと呼ばれ、「生産性向上」と「原価低減」を行うものです。ジェムコでは、「IE」の考え方に関する情報をコラムでお届けしております。
今回は、「第51回 検査のポイント①」についてです。
付加価値を生まない検査は、なくすのが理想的
付加価値を生まない検査は、本来は「不良対策の徹底」と「工程信頼度の向上」によってなくすのが理想的です。しかし、現実にはそれがなかなか難しいものです。
そこで検査を行なわざるを得ないわけですが、品質検査のためのチェック・測定をどこですべきかというのは重要な問題です。最終検査ですべての項目を検査すると、合理的かもしれません。しかし、もし不具合が見つかったときの対処が難しくなります。製品を分解して修正してから再度組み立てることも必要になるかもしれません。それが不可能なら、廃棄ということになります。製品ができてしまってから直すと言うのは、手間とコストがかかります。
どこで検査をするのが合理的?最適検査ポイントを見つける必要性
もし、検査で引っかかる不具合がどこで発生しているのか特定できるなら、そこで検査するのが最も合理的です。そこで修正して次の工程へ送れば、良品だけが流れることになり、最終検査の手間が大きく削減できることになります。
ただし、やたらと検査ポイントを増やすのは好ましくありません。停滞を生みやすくなり、リードタイムが長期化します。最適検査ポイントを見つける活動が必要になります。
ある工場での話
ある電気製品製造工場の話です。
工程途中の中間検査がなく、最終検査で徹底的な検査を行っていました。そこで見つかる不具合項目は多いときで50件以上もあり、その修正に時間がかかっていました。
試しに中間検査を行い、工程途中での修正をするようにすると、リードタイムは最終検査完了でほとんど差がなく、基板をはずしたりする大掛かりな修理の数は激減しました。そこで本格的に中間検査を導入するための不具合発生箇所のデータ収集と分析によって、最適な検査ポイントを設定して運用を開始しました。最終検査の負荷が減り、テープなど一度使用したら再使用できない消耗品の消費量削減、特に特急品の後戻りがほとんどなくなったことなどのメリットを生み出すことができました。
中間検査が多すぎる工場では?
逆に中間検査が多すぎる工場では、検査ポイントごとに発見される不具合の内容と件数、修正時間のデータを取って、同様に最適検査ポイントを設定してポイント数を減らしたこともあります。
工場や製品の特性に合わせた最適検査方法と検査ポイントの見直しはロスを削減する有効な手段です。