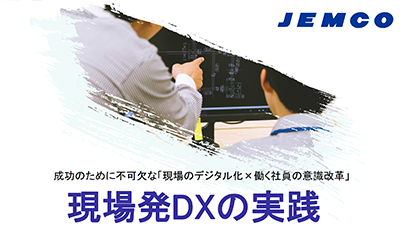【5Sはなぜ必要なのか】必要性と上手く進めるポイントとは?
文責:ジェムコ日本経営
5Sは、整理・整頓・清掃・清潔・しつけの5つの言葉からよばれているもので、職場の環境維持や業務効率を上げることを目的とした活動です。「片付けと何が違うのか?」その必要性と上手く進めるポイントについて考えます。
目次
「5S」とは?=整理・整頓・清掃・清潔・しつけ
5Sは、整理・整頓・清掃・清潔・しつけの5つの言葉のローマ字表記の頭文字に基づいてよばれているもので、職場の環境維持や業務効率を上げることを目的とした活動です。
■整理(Seiri)
■整頓(Seiton)
■清掃(Seisou)
■清潔(Seiketsu)
■しつけ(Shitsuke)
5SはQCD(品質・コスト・納期)の向上に直結
5S(整理・整頓・清掃・清潔・しつけ)については、「単なる片付けなのでは?」と考える人もいるかもしれません。
しかし職場において5Sは、単なる片付けではなく、企業経営の基盤を築き、継続的な改善を促すための重要な活動です。特に製造業では、QCD(品質・コスト・納期)の向上に直結するため、その必要性が高く認識されています。
下記でその必要性について紹介します。
5Sの必要性①品質向上
清潔で整理された職場環境にすることは、製造現場などにおいて異物混入や製品の汚損を防ぐことに繋がります。そのことにより、不良品の発生も減るでしょう。また、作業標準などルールが守られることで作業のバラツキがなくなれば、品質の安定にもつながります。
5Sの必要性⓶安全性向上
乱雑な現場は、資材や工具によるつまずき・転倒などの事故のリスクを高めます。5Sを徹底することで、整理・整頓でき、設備の不具合なども早めに発見できれば、事故を未然に防ぐことが可能になります。
5Sの必要性③生産性向上
5Sの中でも特に整理・整頓により、工具や部品、資料などの「必要なものが必要な時に、必要なだけ、必要な場所にある」状態が実現します。その為、探すといったムダな時間が削減され、本来の作業に集中できるようになり、生産性が向上します。
5Sの必要性④コスト削減
5Sの中でも特に整理・整頓により、不要なものを排除し、在庫を適正に管理できます。それにより、無駄な在庫や保管スペースなどのコストが削減できます。
5Sを成功させるためのポイント①「なぜやるのか」目的を明確に
みなさまのなかには「5S活動をしたことがあるが失敗してしまった」という方もいるかもしれません。
5S活動が失敗する最大の原因は、「ただの掃除や片付け」で終わってしまうことです。
形式的な活動で終わってしまわないよう、「なぜやるのか」目的を明確にし、皆に共有することが重要でしょう。やらされてるという意識になるのはよくありませんから、「5Sをすることで仕事がスムーズになった」というようなことを感じてもらえるようにしていくことが大事かもしれません。
5Sを成功させるためのポイント②行う順番
そして、「5Sと行う順番」にも注意をしましょう。下記のような流れで行うことがいいといわれています。
<5Sと行う順番(1から行う)>
1S=整理
2S=整頓
3S=清掃
4S=清潔
5S=しつけ
5S活動は、まず「整理」から順番に進めることが重要です。間違った順番で5Sを⾏なってしまうと、⼆度⼿間が発⽣する恐れがあります。
そして、最後に「清潔」と「しつけ」によって継続・定着させることが最も重要です。
「ただの掃除や片付け」で終わらせず、働く人の意識を変え、問題を顕在化させ解決する活動として継続させましょう。