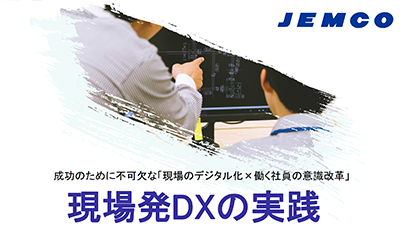生産の基本論~ものづくりの達人になるためにおさえるべきツボ~【第36回 停滞品】
文責:ジェムコ日本経営 コンサルタント 原 正俊
皆さんは、「IE」という言葉をご存じでしょうか?IEは、Industrial Engineering の略称で「生産工学」などと呼ばれ、「生産性向上」と「原価低減」を行うものです。「IE」の考え方に関する情報をコラムでお届けしてまいります。
36回目の今回は、「停滞品」についてです。
モノが止まる理由の1つ「保留品」
工程の途中で溜まってしまう「加工待ちの仕掛品」のほかに、様々な理由でモノが止まってしまいます。
その1つが「保留品」です。保留品と一口に言ってもいろいろなものがあります。
保留品① 加工ストップ
加工ストップは、何らかの理由により加工をストップされた仕掛品です。この確認をきちんとしないと、いつまでも保管する羽目になります。一定の期間を決めて、それ以上顧客都合でストップする場合は顧客へ送ってしまうことも、顧客との間で決めなければなりません。あるいは当社で保管する場合には保管料を請求することは正当な権利です。
保留品② 品質確認
顧客・自社どちらの原因でも、品質的に問題がある場合や確認が必要な場合には、出荷ストップや加工ストップの可能性が考えられます。その場合、すみやかに結論をだすようにしましょう。
顧客へ確認してもらうケースは別ですが、社内での品質確認プロセスであればいつまでに結論が出るのかははっきりしているはずです。
この品質確認のための停滞が頻発するようでは、社内の品質体制に問題がある可能性が高いので、その部分からの根本改善が求められます。
保留品③ 材料不足
最も避けるべきは、この材料不足による停滞です。これは加工がスタートしてから、材料が一部不足したり、入荷が遅れて作業ができなくなり停滞するというものです。特に組立系の工場で発生します。
組立を途中まで行って、部品の到着を待ってから続きを行うのはロスが大きすぎます。加工に着手するのは部品がすべて揃ってから、というルールを徹底しましょう。
保留品④ キャンセル
何らかの事情によって、加工開始してから顧客よりキャンセルがくることは当然考えられます。その場合のルールを決めていますか?
材料費や加工費を請求するのはもちろんのこと、管理費や廃棄費用も請求しなければなりません。その取り決めがあいまいで、交渉中にずっと仕掛品が停滞していることは避けなければなりません。
対応で大切なこと
何より大事なことは、停滞品は「何故停滞しているのか」「担当者は誰か」「いつまで保管するのか」を明記した表示を品物に貼っておくことと、場所を決めてそこに保管するということです。何だかわからないものが工程の中にいつまでも置かれているという事態は避けなければなりません。