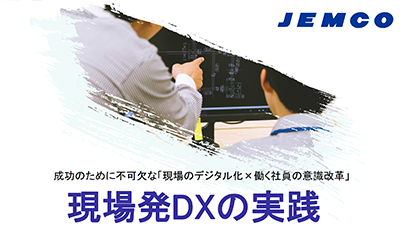生産の基本論~ものづくりの達人になるためにおさえるべきツボ~【第47回 停滞と不良】
文責:ジェムコ日本経営 コンサルタント 原 正俊
皆さんは、「IE」という言葉をご存じでしょうか?IEは、Industrial Engineering の略称で「生産工学」などと呼ばれ、「生産性向上」と「原価低減」を行うものです。ジェムコでは、「IE」の考え方に関する情報をコラムでお届けしております。
今回は、「第47回 停滞と不良」についてです。
どんな不良問題が発生しているか?
皆さんの工場ではどんな不良問題が発生しているのでしょうか。
いろいろな工場で不良削減の活動を支援してきた経験から言うと、キズなどの「外観の良否に関わる不良」と、異物など「本来あってはならないモノが紛れ込んでいる不良」というのが対象テーマとして多いようです。
それだけ外観や清潔感にこだわるということでしょうか。
キズ不良はどこで発生している?
キズ不良は、どこで発生しているのでしょうか。
製造途中でしょうか。それとも輸送中でしょうか。それが分かれば対応もしやすいものです。しかし、なかなかそれが見つけられないというのが実情ではないでしょうか。
発生の可能性としての「仕掛品」
1つの可能性として、仕掛品というのがあります。仕掛品とは、製造に取り掛かってはいるものの、製造途中での製品のことです。
停滞中に何かがぶつかったり、動かしているときにこすれて傷が付いたりということも考えられるはずです。ということは、停滞時間が少ないほどその危険性が低くなるといえます。それも停滞を少なくするべきであるという主張の根拠になります。
異物は停滞中に入り込んでくる可能性が高い
停滞時間が長くなったり、モノが動く頻度が高くなるほど、キズがつく危険性は高まります。
さらに、異物は停滞中に入り込んでくる可能性が高いです。異物不良の対策をするときに発見される異物の分類を行い、進入経路を特定することはよくおこなわれています。その経路は停滞しているところというのが意外と多いのです。
キズや異物など代表的な不具合は停滞と深いつながりがあります。停滞がなければ、それだけ不具合発生の危険性が低くなるということなので、その意味からも停滞削減を徹底していただきたいものです。