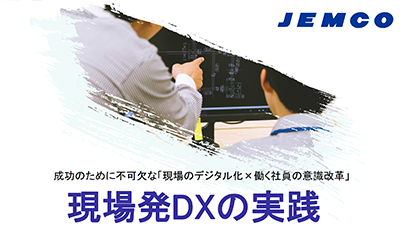生産の基本論~ものづくりの達人になるためにおさえるべきツボ~【第48回 変化点】
文責:ジェムコ日本経営 コンサルタント 原 正俊
皆さんは、「IE」という言葉をご存じでしょうか?IEは、Industrial Engineering の略称で「生産工学」などと呼ばれ、「生産性向上」と「原価低減」を行うものです。ジェムコでは、「IE」の考え方に関する情報をコラムでお届けしております。
今回は、「第48回 変化点」についてです。
不良は工程のどこで発生している?
不良は工程の途中では、どこで発生しているのでしょうか。
それは工場の特性や状況にもよりますが、特定するのが非常に難しいものです。特に、発生する頻度の低い不具合は、発生事象を確認することが困難です。発生する場所が特定できていれば、ビデオの撮影で発見できることも可能でしょう。そうでなければ不具合発生状況から推測するしかありません。
考えられる発生原因や発生のメカニズムをできるだけたくさん挙げて、順番に潰していくという地道な作業になります。その発生の可能性という点では、製造途中での変化点を管理するのも一つの方法です。
「変化点」と「変化点管理」
「不良は工程が変化するときに起きやすい」という仮説の元に、変化が起きたときを「変化点」といって、その前後の工程検査や不具合チェックを強化することを「変化点管理」といいます。
作業の中の変化には下記のようなことが挙げられます。
□作業する人が交替等で変わった
□材料のロットが変わった
□配置が変わった
□加工する設備が変わった
作業の順序が変わることも何らかのトラブル要因となる可能性
作業の順序が変わることも、変化の1つです。
作業を観察していると、順序が分かることをよく見かけます。次の工程の仕掛品が溜まっているので、他の作業をしたり、手順を変えるということをしばしば行っているのではないでしょうか。
それは工程の作業が、同じ順番で繰り返されていないということですから、何らかのトラブル要因がある危険性があります。いくつかの仕掛品を接近しておいて置くことで接触してキズがつくなど、通常うまく流れているときには起こりえないことが起こるのです。これも変化と捉えてそれを禁止するか、監視対象とすることで意外に気が付いていない変化に対応することができるのです。