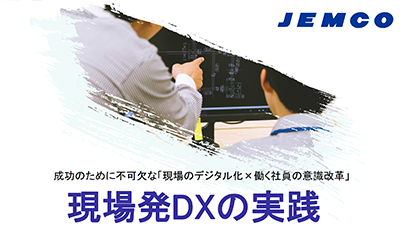生産の基本論~ものづくりの達人になるためにおさえるべきツボ~【第50回 測定の思い込み】
文責:ジェムコ日本経営 コンサルタント 原 正俊
皆さんは、「IE」という言葉をご存じでしょうか?IEは、Industrial Engineering の略称で「生産工学」などと呼ばれ、「生産性向上」と「原価低減」を行うものです。ジェムコでは、「IE」の考え方に関する情報をコラムでお届けしております。
今回は、「第50回 測定の思い込み」についてです。
機械部品を加工する、ある工場での話
ある支援先の工場での話です。
そこでは、高度に精度を要求される機械部品を加工していました。
丸棒状の部品を加工して、それに歯車部品を取り付ける工程の改善を検討しました。その丸棒部品は、歯車部品を取り付けた後の偏芯が製品品質に大きな影響を与えます。偏芯の度合いを測定する検査機械を使用して、歯車部品を取り付けたあとの丸棒のぶれを全品測定していました。そうすると「OK」と「NG」が検査機のモニターに表示されると同時に、偏芯を補正するためのウエイトを取り付ける位置を指示してくれます。そのウエイトを取り付けてこの工程は完了。次の工程へ部品が送られていました。
この工程の懸念点
このときウエイトは、かしめて取り付ける方式なので、かしめ機の振動が製品に伝わります。その振動の影響が気になったのと、かしめた後のウエイトの形状、つまりつぶれ具合が一定でないことに不安を覚えた私は、作業者にウエイトを取り付けてかしめた後の製品を再度測定するようにお願いしました。
「1回測定すれば大丈夫」という思い込み
そうすると案の定、偏芯の検査機でNGが出るではありませんか。
今まで偏芯補正されていた製品が、実は再びウエイトのずれによって偏芯を引き起こしていたのです。それに気が付かず、「偏芯補正すればOK」と思い込んでいたところに問題がありました。
これは「1回測定すればそれで大丈夫」という思い込みがあったためで、補正値と位置を決定するための測定は検査測定ではないということが理解されていなかったということを示しています。
この後の工程を経て、製品になった時の最終検査で引っかかる不具合の原因のひとつがこの部品の偏芯である可能性があり、改善することで不具合の解消に貢献できました。