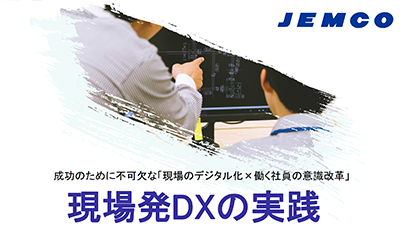生産の基本論~ものづくりの達人になるためにおさえるべきツボ~【第55回 エネルギーのロス】
文責:ジェムコ日本経営 コンサルタント 原 正俊
皆さんは、「IE」という言葉をご存じでしょうか?IEは、Industrial Engineering の略称で「生産工学」などと呼ばれ、「生産性向上」と「原価低減」を行うものです。ジェムコでは、「IE」の考え方に関する情報をコラムでお届けしております。
今回は、「第55回 エネルギーのロス」についてです。
製品の価値向上に使われているエネルギーはどれくらい?
製品の価値向上に使われているエネルギーは、工場で使用されるエネルギー全体の何%でしょうか。それを正確に測定するには、専用の機器を使用して調査しなければならず、簡単にはわかりません。
ロスエネルギーが多く発生している
工場を歩いてみると、実に多くのエネルギーがロスされていることが分かります。例えば下記のようなものです。
□ 加工や運搬をしていないのに回転しているモーター
□ 稼働していないけれど電気が入っていて待機している設備などの動力エネルギーのロス
□ あちらこちらで洩れていたりカバーされていないために熱が逃げているロス
□ 誰もいないのについている照明などのロス
ロスの定量化は「ロスマップ」を作成するとわかりやすい
これらのエネルギー関連のロスは、項目別に問題箇所を洗い出して、ロスの定量化を行います。このときに「ロスマップ」を作成すると、非常にわかりやすくなります。工場配置図などに問題箇所を明記して、問題事象と対処対策を記載します。このときに色別管理を行います。例えば赤は未対策、黄色は対策中あるいは対策検討中、青は完了、緑は先送りなどのように色ごとに状況を決めておき、問題箇所に印をいれます。さらに問題箇所の写真を貼り付けておくと分かりやすくなります。これも状態の視覚化といえます。
過剰なエネルギーも改善の対象
過剰なエネルギーも改善の対象になります。ある工場では乾燥工程でLPGを燃焼させていました。一定の熱量を維持することが仕事となっていました。乾燥終了後の水分量を測定すると過乾燥になっていることがあり、乾燥のための熱量が大きすぎるのではないかという仮説が成り立ちました。試しに熱量を下げて燃焼させて通常通り乾燥工程を通過したものを測定してみると規定値に入っていました。つまり今まで熱量のほうだけ注目していたけれど、水分量にあまり注意を払っていなかった、本来管理すべきなのは水分量であるのに間違った管理をしていたことが分かったのです。もちろん熱量を下げてエネルギーコストを削減したことは言うまでもありません。
管理すべき事項が不適当であるケースはこのほかにも見つかり、過剰あるいはムダなエネルギーの削減につなげることができました。日ごろ見過ごされているエアー洩れや熱洩れもきちんと対処すればコスト削減につながります。エネルギーには敏感にならなくてはなりません。