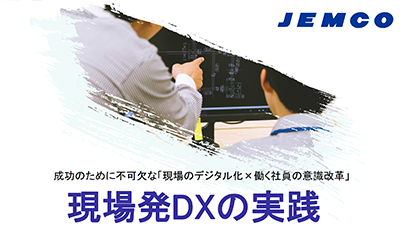生産の基本論~ものづくりの達人になるためにおさえるべきツボ~【第56回 材料のロス①】
文責:ジェムコ日本経営 コンサルタント 原 正俊
皆さんは、「IE」という言葉をご存じでしょうか?IEは、Industrial Engineering の略称で「生産工学」などと呼ばれ、「生産性向上」と「原価低減」を行うものです。ジェムコでは、「IE」の考え方に関する情報をコラムでお届けしております。
今回は、「第56回 材料のロス①」についてです。
製品とならない材料とは?
製品とならない材料はすべてロスと考えなくてはなりません。製品とならない材料はどんなものがあるでしょうか。
例えば、下記の6つが挙げられます。
①不良や瑕疵で製品の材料として使用できないもの-材料そのものの不具合
②製品が不良品となり廃棄された場合の使用材料
③歩留まりの悪さによる使われない端材
④切り粉やカスとして排出される廃棄品
⑤計画や予測のずれによる使用せずに廃棄する材料
⑥設備の立ち上がりや調整の時に使用される試し加工のための材料
これらは、材料として購入したのに製品にならなかった部分です。これを削減していくことで、材料変動費を下げていくことが可能となります。
材料ロスが大きい業種も
業種によっては、この材料ロスが大きいところがあります。
例えば、製品の歩留りがかなり低い製紙工場を視察したことがあります。もちろんほとんど材料として再利用できるので、本当の意味での廃棄ロスは少ないのかも知れません。しかし、製品として完成したものを再度原料として利用するということは、1回目の生産に使われた材料以外のリソースがロスになっているということです。
再利用にはコストがかかる
ここで意識が低いところは、「ロスを出している」ということ。また原料として使えるから問題ないと考えているとしたら大きな誤りです。再利用にはコストがかかるということを認識してください。
直行率という言葉がありますが、これは製品として完成したものがそのまま補修も再加工もされずに出荷される割合を表します。先ほどの製紙工場の例では、廃棄・再利用されずにそのまま製品として出荷される割合が低いように感じました。同じようなことが印刷工場でも見かけられ、廃棄される印刷物が物凄く多いところがあります。
廃棄や再利用する材料の割合を低くするように、技術的な改善を検討・実施してもらいたいものです。