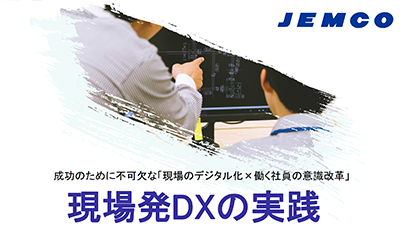生産の基本論~ものづくりの達人になるためにおさえるべきツボ~【第58回 違算の防止】
文責:ジェムコ日本経営 コンサルタント 原 正俊
皆さんは、「IE」という言葉をご存じでしょうか?IEは、Industrial Engineering の略称で「生産工学」などと呼ばれ、「生産性向上」と「原価低減」を行うものです。ジェムコでは、「IE」の考え方に関する情報をコラムでお届けしております。
今回は、「第58回 違算の防止」についてです。
違算とは?
違算とは、帳簿上あるいはコンピューター上の在庫量と実際の在庫量が食い違っていることを指します。
実際の在庫量は様々な原因で登録上と異なってきます。例えば、
①不良が発生して再生産のために新たに材料を払い出した
②現場で余った材料や部品を倉庫に戻した
③陳腐化した材料を廃棄した
④調整材が予定以上に必要だった
これらのことが起きたときに正確にコンピューターに受け払いを入力すれば違算は発生しません。しかし実際には入力を忘れたり、面倒がってやらなかったりということがおきます。
どのようなロスが発生する?
では、違算が発生した場合はどのようなロスが発生するのでしょうか。
①違算が発生した原因を追求するためのロスが発生
基本的には違算の原因を突き止め修正しなければなりません。その調査をしたり、再度数量を数えたりすることに時間がかかり、ロスとなります。
②原因が突き止められなければ会計的な処理を行う⇒事務的な手続きのロスが発生。
違算のうち不足分については、保留品などから見つかることがあります。そのようなとき再び会計的な処理をすると二重のロスとなってしまいます。
原価計算が不正確になる原因に
違算は、材料費などの原価計算においても不正確になる原因となります。使用量が不正確になってしまうからです。受け払いの部門や担当者を決めて、そこを通さないと材料や部品が払いだしてもらえないというしくみも有効でしょう。誰でも自由に材料を持っていけるとしたら必ず違算が起きます。材料は現場で保管させない、必ず返却させる、倉庫の管理を受け払い担当だけに限定し、勝手に材料を持っていくことを禁止する、といったルールの徹底も必要です。
そして、材料の受け払いのときには、正しい処理を正しいタイミングで行うようにしましょう。